イベント
2025.11.24
文学部 歴史文化学科
【歴史文化学科】公開講座「中世寺院と地域社会-南河内を中心に-」を開催しました
11月22日(土)、本学博物館にて公開講座「中世寺院と地域社会-南河内を中心に-」を開催しました。中世日本では寺院が社会の中心的な存在の1つでした。今回の講座では河内長野の古刹・金剛寺を中心に、女院や信仰、寺領、民衆、商人などの様々な切り口で寺院と地域社会の関係に迫りました。
まず、最初の講演は大阪大学名誉教授・川合康先生の「女院の高野信仰と河内国金剛寺の成立」です。金剛寺の成立過程について、草創期の性格や女院の高野信仰、高野参詣における交通路と河内長野の役割などをもとにお話いただきました。

続いて相愛大学の永野弘明先生より「中世南河内における寺領と民衆」と題してお話いただきました。金剛寺を中心とする天野谷一帯に広がる寺辺領とそこに関わる人々の様相について、中世前期から後期まで長いスパンで捉えて解説いただきました。

最後に本学の伊藤大貴講師が「戦国期南河内の寺院と商人」というテーマで講演しました。金剛寺文書に登場する硯屋宗悦という商人にスポットを当て、金剛寺にて調査した新出史料などをもとに彼の素性や人脈、金剛寺との関係を概説しました。
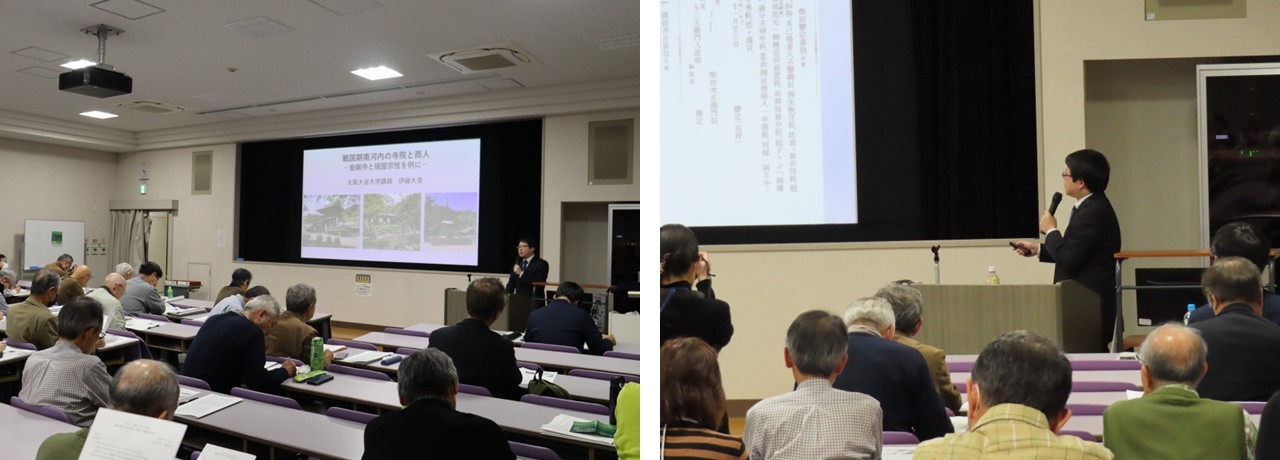
講演終了後の質疑応答ではたくさんのご質問をお寄せいただき、本テーマへの関心の高さを感じ取りました。当日は大勢の方にお越しいただき、盛況のうちに終わることができました。川合・永野両先生ならびにご来場いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
